教育情報の公表
Disclosure of Educational Information
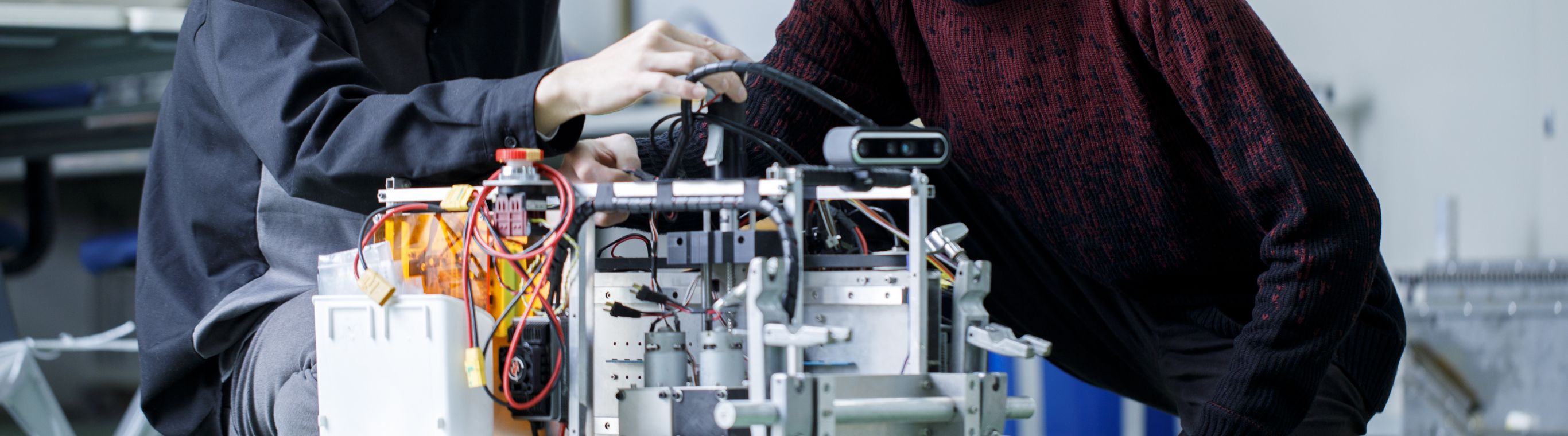
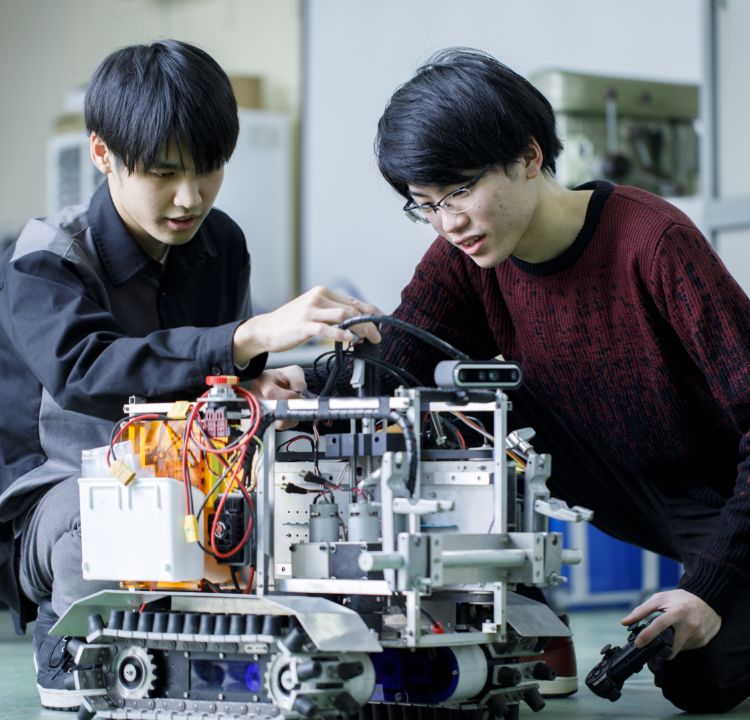
WEBシラバス
SYLLABUS
- 講義名
- 卒業研究(4N)
- ナンバリング
- EN43-GR1-G-11
- 開講学部学科
- 工学部原子力技術応用工学科
- 開講学年
- 4年
- 開講期
- 通年
- 担当者
- 三島 史人
- 単位数
- 6
- 授業の目的
- 大学での学修の集大成として、4 年次の1年間、所属学科の各教員による指導のもとでそれぞれ特定のテーマを設定し、主体的に研究を行う。最先端の研究の一翼を担うことで、研究におけるものの考え方や研究の進め方を学び、研究者・技術者としての倫理観も身に付ける。卒業研究では、1年間にわたって実験的研究、理論的研究、あるいはコンピュータシミュレーションなどの研究を行い、得られた研究成果を卒業研究論文にまとめ、卒業研究発表会で発表する。これらを通して、研究・開発の進め方あるいは研究成果の報告及び質疑応答の技術などを修得する。(時間数の一例:90分×2時限×30回)
本授業は、対面授業とする。ただし 何らかの理由で対面での授業実施が困難な状況となった際、 オンライン授業となる場合がある。 - 科目に関するDP
(ディプロマポリシー) -
- 特に重要
- 重要
- 望ましい
- 学修到達目標
-
1 定められた研究テーマに基づいて自ら研究計画を立て、それに従って研究を遂行する能力を修得する。
2 研究テーマに関連する資料や情報を収集し、研究の位置づけを理解する能力を修得する。
3 和文もしくは英文で記された参考文献を読み、自分の研究に反映させるとともに、適切に引用できる能力を修得する。
4 研究の背景にある本質的な問題を理解し、それを論理的に分析・解決する能力を修得する。
5 研究結果を整理し、得られた成果の意義や有効性を文章や図表でわかりやすく表現できる能力を修得する。
6 研究成果を口頭で論理的に発表し討論を行う能力を修得する。
- アクティブラーニング講義形態
- グループディスカッション、プレゼンテーションと質疑応答
- 関連科目
- 原子核反応学、原子炉プラント工学、核燃料工学、放射線化学、放射線応用工学、放射線照射工学
- 評価方法
- 卒業研究の評価は、研究成果をまとめた卒業論文だけでなく、1年間を通しての研究テーマへの取り組みも対象となる。その中には、年間通して行われる研究室での勉強会や報告会への参加、卒研中間発表会での発表態度なども含まれる。したがって、卒業研究への取り組み、研究テーマに対する理解度、問題の発見と実験や数値シミュレーションなどによる論理的な解決、得られた成果の有用性、発表と質疑応答、卒業論文のまとまりなどについて、目標に対する学修到達度の観点から総合的に評価する。
- 受講心得
- テーマに関連する研究資料、論文、参考書等を用いて各研究室で行われる勉強会等に十分な準備をしたうえで参加し、活発に議論すること。卒業研究は1年間にわたって行うものであるため、計画的に研究を進めるように心がけること。
- 関連リンク
授業計画
| 1 | テーマ | 卒業研究の構成 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内容 方法等 |
卒業研究は、その性格上、通年における各週の授業計画を示すことはできないが、標準的には以下の項目から構成される。 1. 研究室ゼミ(研究の進捗状況の報告・討論、文献調査等による論文紹介、輪講など) 2. 指導教員との研究打ち合わせ 3. 必要な実験手法、解析手法、数値シミュレーション手法などの修得 4. 実験や数値シミュレーションの遂行 5. 研究室での報告会(レポート作成、プレゼンテーション、討論) 6. 卒業論文のまとめ |
|||
| 事前 学修 |
卒業研究を遂行するために必要な情報を自ら収集し、知識を修得する。 | 時間(分) | 80 | |
| 事後 学修 |
実験等で得られた結果についてはその日のうちにまとめ,図表等を用いてわかりやすく整理する。 | 時間(分) | 100 | |
| 2 | テーマ | 卒業研究の進め方(1) 「実施:4月~1月中旬」 | ||
| 内容 方法等 |
指導教員からの説明をよく聞き、卒業研究のテーマを選定する。その後、指導教員の指導のもとで研究計画を立て、主体的に取り組む。研究を行うにあたっては、指導教員と常に緊密に連絡を取り合いながら、必要に応じて随時指導を受ける。卒業研究の期間中、通常毎週1回程度行われる研究室の報告会に出席し、実験の結果や研究の進捗状況、研究テーマに関する文献調査や情報収集について報告する(卒業研究の進め方は研究室ごとに異なるので、それぞれの指導教員の指示に従うこと)。 | |||
| 事前 学修 |
卒業研究を遂行するために必要な情報を自ら収集し,知識を修得する。 | 時間(分) | 80 | |
| 事後 学修 |
実験等で得られた結果についてはその日のうちにまとめ,図表等を用いてわかりやすく整理する。 | 時間(分) | 100 | |
| 3 | テーマ | 卒業研究の進め方(2) 「論文提出:1月下旬」 | ||
| 内容 方法等 |
卒業研究の成果については、論理的な記述で卒業論文としてまとめる。卒業論文は、事前に指導教員による閲読や口頭試問を受け、学科で定める期日を厳守して学科に提出する。したがって、十分な時間の余裕をもって論文作成にあたること。学科に提出する際、予め決められた書式や論文内容が所定のものに合致していないと受理されないので十分注意する。また、期日までに提出できなかった場合には、原則として評価の対象としない。 | |||
| 事前 学修 |
論文作成に必要な実験結果、解析結果、シミュレーション結果について取り纏め論文の構成を考える | 時間(分) | 80 | |
| 事後 学修 |
指導教員からの指摘事項を基に論文の推敲、修正を行う | 時間(分) | 100 | |
| 4 | テーマ | 卒業研究の進め方(3) 「卒業研究発表:1月末」 | ||
| 内容 方法等 |
卒業研究の意義や成果を、決められた時間内でパワーポイントを用いて口頭でわかりやすく発表する。発表後の質疑応答においては、質問の内容をよく理解した上で、研究結果や収集した資料・情報に基づいて論理的且つ簡潔に回答する。 | |||
| 事前 学修 |
卒研発表の手間のパワーポイントの作成、発表手順、発表内容について充分何件等を行う | 時間(分) | 80 | |
| 事後 学修 |
卒研発表における質問、コメント、回答について、十分な検討と、省察を行い、必要に応じて指導教員の指導を受けて今後の研究に生かす | 時間(分) | 100 | |
教材・参考書
| No. | 分類 | 書籍名 | 著者名 | 出版社 | 価格 | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教材 | 適宜指示する | ー | ー | ||
| 2 | 参考書 | 適宜指示する | ー | ー |


