教育情報の公表
Disclosure of Educational Information
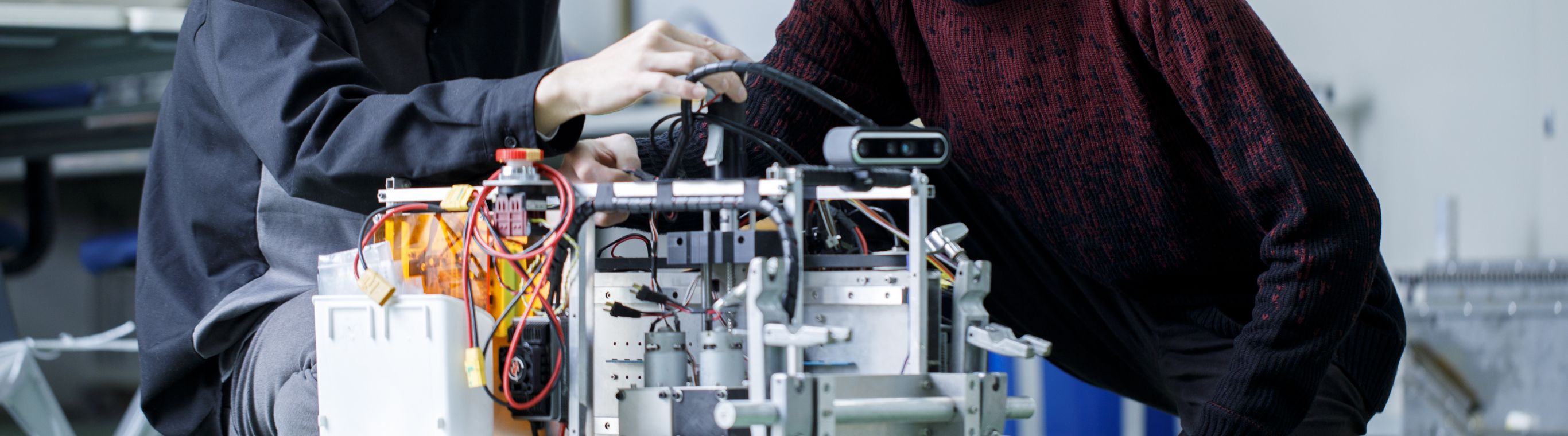
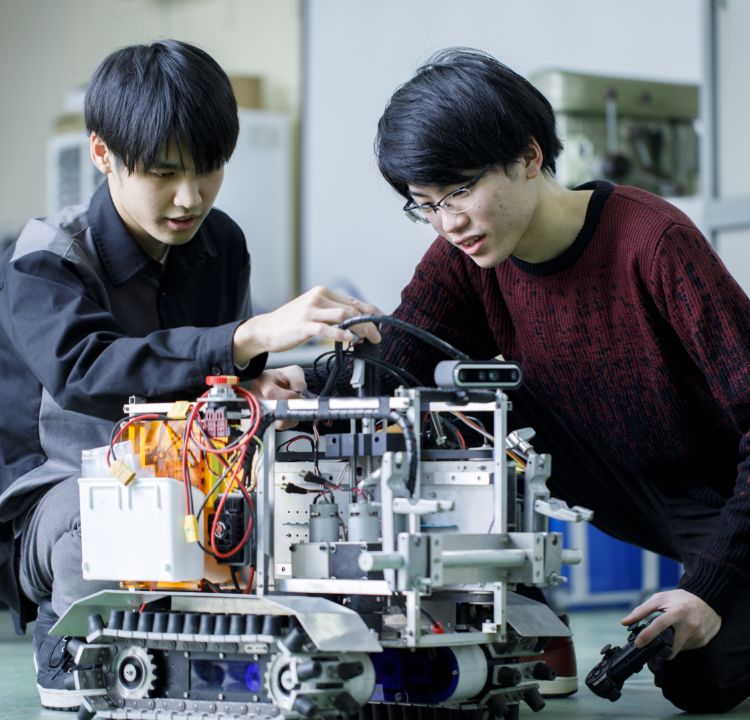
WEBシラバス
SYLLABUS
- 講義名
- プロジェクトスタジオⅢ(2MD)
- 開講学部学科
- 大学院社会システム学専攻デザイン学コース
- 開講学年
- 2年
- 開講期
- 前期
- 担当者
- Dコース所属教員
- 単位数
- 2
- 授業の目的
- 学内組織「F’s Design Studio」において受託したデザイン実務への参加、学術研究の社会実装や無償ボランティアとして行う社会貢献活動などを単位認定する科目である。産学連携・社会貢献・デザインコンペティションなど、所属研究室あるいはデザイン学教室において教員の指導の下に実施されるデザイン活動が対象となる。社会の中で必要とされる作品制作のプロセス、デザイン実務の方法、共同作業を円滑に進めるためのコミュニケーションスキル、デザイナーの職能などについて実践的に学ぶ。(時間数:90分×2時限×15回)
- 科目に関するDP
(ディプロマポリシー) -
- 特に重要
- 3
- 重要
- 1
- 望ましい
- 2
- 学修到達目標
-
1 プロジェクトの依頼先が何を求めているかを的確に捉えるためのコミュニケーションが適切にできる
2 理論的・思想的・芸術的観点から、価値のあるコンセプトの設定および展開ができる
3 学術的・技術的・社会的・経済的観点から価値のある成果物を制作できる
4 説得力があり、魅力的なプレゼンテーションができる
- アクティブラーニング講義形態
- ワークショップ形式で授業を実施する
- 関連科目
- 創造技法特論、住環境デザイン特論、空間デザイン特論、プロダクトデザイン特論、視覚伝達デザイン特論
- 実務経験のある教員による授業
- 教授陣はデザインの実務経験が豊富な教員で構成され、社会実装を意識した実践的な指導を行う
- 評価方法
- 担当した成果物の評価(80%以上)および取り組みへの姿勢と意欲(20%未満)により総合的に評価する。
- 受講心得
- 作業は授業時間だけで終わらないので、覚悟を持って取り組むこと。院生には4年生以下の学生を指導する役割も期待されている。
- 関連リンク
授業計画
| 1 | テーマ | オリエンテーション | ||
|---|---|---|---|---|
| 内容 方法等 |
実施するデザイン活動の概要説明および役割分担の確認を行う | |||
| 事前 学修 |
関連する先行事例を調査すること | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 90 | |
| 2 | テーマ | イントロダクション | ||
| 内容 方法等 |
課題の条件を理解する、あるいは依頼主の要望を聞き取り、問題の所在を確認する | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 3 | テーマ | 先行事例調査・参考作品収集 | ||
| 内容 方法等 |
関連する先行事例の調査、参考になる作品の事例を収集する | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 4 | テーマ | 方向性の設定 | ||
| 内容 方法等 |
最初のアイデアを出し、与条件(期間、予算、依頼主の要望など)のなかで、可能性のある解決策の範囲を探る | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 5 | テーマ | 構想案の検討 | ||
| 内容 方法等 |
アイデアにもとづき、最初のラフスケッチを用意する | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 6 | テーマ | 中間発表およびディスカッション | ||
| 内容 方法等 |
最初の構想のまとめと、それをめぐるディスカッションを行う。依頼主がある場合は、方向性の確認を行う。 | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 7 | テーマ | 全体構想をめぐる軌道修正 | ||
| 内容 方法等 |
視野を広げ、考えられる可能性を検討し、解決策の妥当性を検証する | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 8 | テーマ | 制作活動(基礎) | ||
| 内容 方法等 |
課題解決に向けた実質的な作業を行う | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 9 | テーマ | 制作活動(展開) | ||
| 内容 方法等 |
課題解決に向けた実質的な作業を行う | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 10 | テーマ | 制作活動(詳細) | ||
| 内容 方法等 |
課題解決に向けた具体的な作業を行う | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 11 | テーマ | 制作活動(表現) | ||
| 内容 方法等 |
課題解決に向けた効果的な表現を模索する | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 12 | テーマ | 制作活動(ブランディング・広報) | ||
| 内容 方法等 |
課題解決に向けた効果的なブランディングや広報活動のあり方を検討する | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 13 | テーマ | 制作活動(完成) | ||
| 内容 方法等 |
課題解決に向け、成果物を完成させる | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 14 | テーマ | 成果の発表 | ||
| 内容 方法等 |
成果物の発表、プレゼンテーション、広報活動を行う | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
| 15 | テーマ | 総括 | ||
| 内容 方法等 |
活動に対して評価を調査し、活動の反省、成果物のブラッシュアップ、作品論文などの形にまとめる | |||
| 事前 学修 |
時間(分) | |||
| 事後 学修 |
デザイン活動は講義時間帯のみでは完了しえないため、時間外での打合せ、作業等が発生する。また、次回講義までに各自が実施しなくてはいけない課題も随時発生する。これらをすべて事前事後学習として取り組むこと。 | 時間(分) | 180 | |
教材・参考書
| No. | 分類 | 書籍名 | 著者名 | 出版社 | 価格 | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教材 | 必要に応じて指示する | ー | ー | ||
| 2 | 参考書 | 状況に応じて指示する | ー | ー |


