教育情報の公表
Disclosure of Educational Information
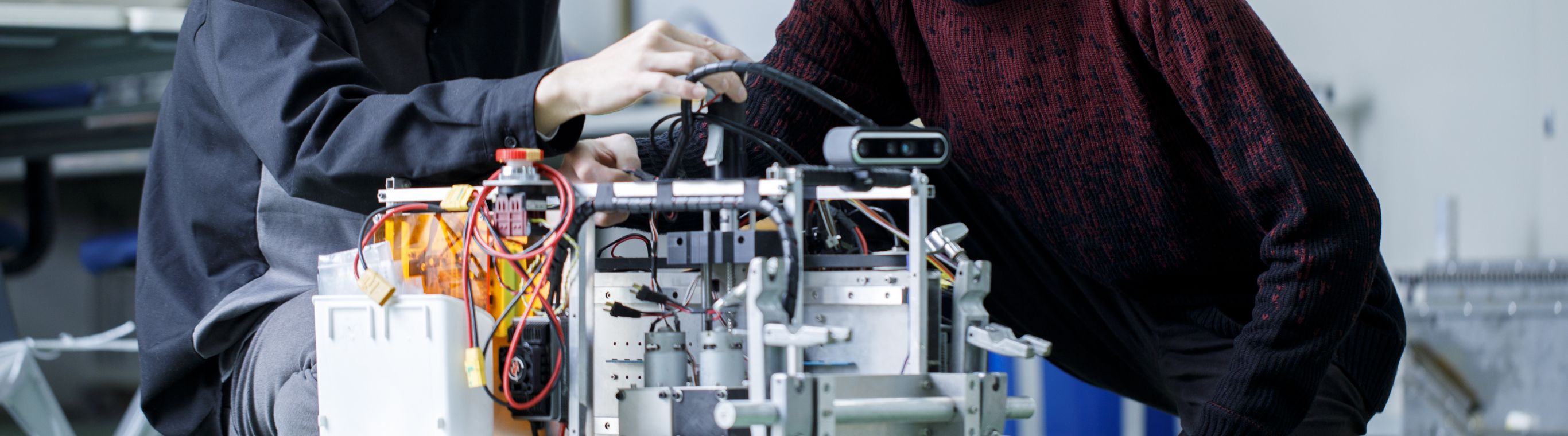
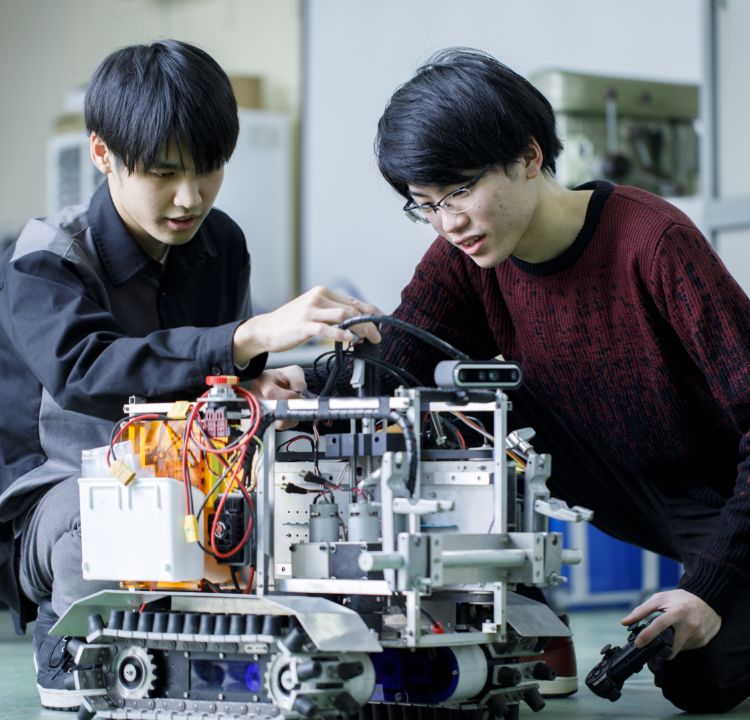
WEBシラバス
SYLLABUS
- 講義名
- 工業科教育法Ⅰ(3EMAND)(教職)
- 開講学部学科
- 教職科目
- 開講期
- 前期
- 担当者
- 北村 泰生
- 授業の目的
- 現在の産業社会における工業教育の意義、役割、目標および教育関係法令を理解しつつ、教科「工業」の教員免許取得を目指す学生に対して、機械系、電気系、建築系、土木系、化学系、情報系、デザイン系などすべての工業高校の学科の教師として必要な知識、「すべての学科に共通な科目」「主な学科の実験・実習」「就業体験」「資格取得」を重点的に学ぶ。
また、工業教育の意義と役割、工業教育の目標、教育課程、授業設計などについて知識を深め、教師として就職した際に、第一線で活躍できるための人材育成を目指す。
90分×2時限×15回 - 科目に関するDP
(ディプロマポリシー) -
- 特に重要
- 重要
- DP1,DP3,DP
- 望ましい
- DP2,DP5
- 学修到達目標
-
1 新学習指導要領が示す工業教育の意義・役割・目標・内容を理解し論述できる。
2 工業高校発展の歴史と現状が理解でき、工業教育の視点に立った学習指導ができる。
3 新学習指導要領による教科「工業」の共通科目、主な学科の実験・実習の内容および実践的工業教育が理解でき、指導できる。
- アクティブラーニング講義形態
- グループ討議、テーマごとの発表と意見交換、模擬授業
- 関連科目
- 工業系学科の専門科目すべて、工業科教育法Ⅱ、職業指導原理、職業指導概論
- 実務経験のある教員による授業
- 小・中・高(校長)・高専・民間企業の勤務経験および公益財団・NPO活動実績を生かし学校と産業社会のつながりを解説
- 評価方法
- 講義を基本としながら、内容の理解を深く・確かなものにするために演習問題や記述問題の解法を行い、成果の提出を求めるとともに、講義テーマに関する発表を求める。
評価は、筆記試験(60%)と毎時間の論述レポート(20%)、および発表内容(20%)の成果を総合する。 - 受講心得
- 本授業は教職科目であることに注目し、常に「教える立場」と「習う立場」を意識すること。
授業のテーマについて口頭発表し、受講者同士の意見交換で考えを述べ合う活動を行う。
自らの考えを明確に論述すること。 - 関連リンク
授業計画
| 1 | テーマ | 職業指導の意義・役割 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内容 方法等 |
教職について(専門性)、工業科の目標はキャリア教育における「基礎的・汎用的能力」、「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」につながる、また高校の工業科は職業の多様化、職業人として求められる知識・技能の高度化への対応を求められている | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、自分の高校時代の教育内容との相違点を探す | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
教職について(専門性)や授業で話した内容を、教師の立場でどのように生徒に伝えるかなどについて、シミュレーションしてみる | 時間(分) | 90 | |
| 2 | テーマ | 工業教育の意義と役割 | ||
| 内容 方法等 |
工業教育の意義と役割、目標、工業教育の役割は①人格の育成、②実践的な職業能力、③論理的思考・合理的処理能力の育成である | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、何故工業教育が必要なのか考える | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
講義内容について、社会と工業教育がどのように結びつくのか考える | 時間(分) | 90 | |
| 3 | テーマ | 工業教育の意義と役割 | ||
| 内容 方法等 |
工業教育の内容と目指す人物像、学習指導要領にみる工業教育の目的やテクノロジストとしての人物像が特徴である | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、産業社会での位置づけを考える | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
講義内容と社会とのつながりを考えてみる | 時間(分) | 90 | |
| 4 | テーマ | 教育関係法令 | ||
| 内容 方法等 |
日本国憲法、教育基本法、学校教育法を元に日本における工業教育が法的な根拠をもって実施されていることを理解する | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、学習指導要領解説を調べる | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
学習指導要領解説をもう一度読んでみる | 時間(分) | 90 | |
| 5 | テーマ | 教育関係法令 | ||
| 内容 方法等 |
産業教育振興法、1951 年(昭和 26)制定の産業教育振興法では、産業教育は中学校、高等学校、大学で行うとされていることを確認しながら工業教育の位置づけを学ぶ | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、学習指導要領解説を調べる | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
学習指導要領解説をもう一度読んでみる | 時間(分) | 90 | |
| 6 | テーマ | 工業高校発展の歴史と現状 | ||
| 内容 方法等 |
日本の工業と工業教育の概観、日本の近代化および産業の高度化、そして戦後の高度経済成長を支えた工業教育について学ぶ | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、日本の近・現代史を調べる | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
日本の工業の発展と工業教育について調べる | 時間(分) | 90 | |
| 7 | テーマ | 工業高校発展の歴史と現状 | ||
| 内容 方法等 |
工業教育の歴史、戦後の工業高等学校の発足、発展・拡大を調べながら工業教育が果たした産業社会の高度化と日本経済発展への貢献を学ぶ | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、日本の近・現代史を調べる | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
日本の工業の発展と工業教育について調べる | 時間(分) | 90 | |
| 8 | テーマ | 工業高校発展の歴史と現状 | ||
| 内容 方法等 |
工業高校の課題、今後の中等工業教育、技術の高度化・多様化への対応や深刻な人材不足、超高齢社会による技術継承の問題などから日本の課題と対応を学ぶ | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、高校の教育と大学の教育を比較する | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
大学工学部での学習と工業高校での学習を比較する | 時間(分) | 90 | |
| 9 | テーマ | 工業科目と原則履修科目 | ||
| 内容 方法等 |
工業の科目、教科「工業」の共通科目(工業技術基礎)、技術教育は単なる「つくる技術」の教育から、環境問題、倫理問題にも触れる教育への改善から「工業技術基礎」が設けられたことを学ぶ | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、学習指導要領解説【工業編】を調べる | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
学習指導要領解説【工業編】をもう一度読んでみる | 時間(分) | 90 | |
| 10 | テーマ | 工業科目と原則履修科目 | ||
| 内容 方法等 |
教科「工業」の共通科目(課題研究)、専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる目的で「課題研究」が設定されたことを学ぶ | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、学習指導要領解説【工業編】を調べる | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
課題研究に関するテーマを社会の中から探す | 時間(分) | 90 | |
| 11 | テーマ | 各分野における基礎科目 | ||
| 内容 方法等 |
教科「工業」の共通科目(実習、製図、工業情報数理)、工業に属する各科目で学んだ知識,技術などを体系的・系統的に理解できるよう要素実習,総合実習及び先端的技術に対応した「実習」を設定したことを学ぶ | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、学習指導要領解説【工業編】を調べる | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
講義内容について、実習のテーマと産業社会との関係を調べる | 時間(分) | 90 | |
| 12 | テーマ | 各分野における基礎科目 | ||
| 内容 方法等 |
機械系、電気系、電子機械系、情報系、建築系、土木系、工業化学系等の学習指導要領が示す目標、内容等を確認する | |||
| 事前 学修 |
次の講義で触れる内容について、学習指導要領解説【工業編】を調べる | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
講義内容について、実習のテーマと産業社会との関係を調べる | 時間(分) | 90 | |
| 13 | テーマ | 各分野における基礎科目 | ||
| 内容 方法等 |
工業専門教科の授業計画、「授業」の考え方捉え方を考える内容 | |||
| 事前 学修 |
授業を計画するための教材の準備 | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
授業内容と計画が妥当だったか振り返る | 時間(分) | 90 | |
| 14 | テーマ | 各分野における基礎科目 | ||
| 内容 方法等 |
工業専門教科の授業計画、科目を決めて授業計画の詳細を作り上げる | |||
| 事前 学修 |
授業を計画するための教材の準備 | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
授業内容と計画が妥当だったか振り返る | 時間(分) | 90 | |
| 15 | テーマ | 各分野における基礎科目 | ||
| 内容 方法等 |
計画した授業を模擬的に実施する、計画内容や準備物が妥当か、また教授手法が適当か相互の授業を検討し合う | |||
| 事前 学修 |
今までの講義内容を見直し、ポイントを整理しておく | 時間(分) | 90 | |
| 事後 学修 |
授業内容と計画が妥当だったか振り返る | 時間(分) | 90 | |
| 16 | テーマ | まとめ | ||
| 内容 方法等 |
講義内容の試験と解答および解説、模擬授業と意見発表 | |||
| 事前 学修 |
今までの講義内容を見直し、ポイントを整理しておく | 時間(分) | 180 | |
| 事後 学修 |
時間(分) | |||
教材・参考書
| No. | 分類 | 書籍名 | 著者名 | 出版社 | 価格 | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教材 | 新しい観点と実践に基づく 工業科教育法の研究 改訂版 | 中村豊久、島田和典、豊田善敬、棟方克夫共著 | 実教出版 | 2850円+税 | ISBN978-4-407-34771-5 |
| 2 | 参考書 | 高等学校学習指導要領解説 工業編 | 文部科学省 | 文部科学省 | ー | ー |


