




パラボラアンテナのパラボラ面は電波を集める役割があります。あわらキャンパスのアンテナのパラボラ面の直径10.26mは北陸最大で、たくさんの電波を集めることができるため、電波をしっかりと捉え人工衛星からの情報を確実にキャッチできます。耳に手の平を添えると音が大きくはっきりと聞き取れるようになるのと同じ原理です。
電波をしっかりと捉えることができるため、直径3m級の小型アンテナと比べると、20倍の高速データ受信が可能です。それだけ大量のデータを一度に受け取ることができるので、大容量のデータ取得を必要とする実用的な人工衛星ミッションを可能にします。また、強力なアンテナ駆動システムを備えており、動きの速い人工衛星を確実に追尾できます。
10mパラボラアンテナシステムは2003年から稼働を開始しました。これまで米国NASAの地球観測衛星TERRAおよびAQUAのデータ受信を安定して実施してきています。また、2011年からは直径2.4mの小型アンテナシステムも加えて、同じく米国NASAの地球観測衛星SuomiNPPのデータ受信も行っています。2012年には、高速通信が可能な特性を活かして日本の超小型衛星RAIKOの運用に参加しました。
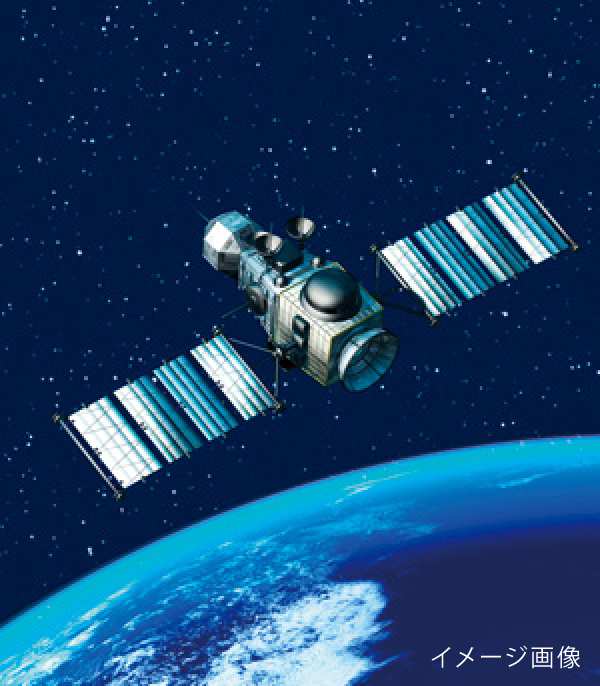
衛星通信では、電波の周波数として、L帯(約1.5GHz)、S帯(約2.2GHz)、X帯(約8GHz)がよく使われます。10mパラボラアンテナでは、周波数選択式の副反射鏡を用いることで、L帯とS帯を1次焦点で、X帯をカセグレン焦点で受信しており、3つの周波数帯の電波を同時に受信できます。つまり、異なる周波数を用いる複数の人工衛星の運用に対応可能です。

受信した地球観測衛星のデータを用いて、若狭湾の赤潮の発生調査、日本海の漂流ゴミの監視、稲の生育状態診断、シカによる森林・農業被害地域の推定、黄砂の検出など、地域に役立つ環境計測の研究を推進しています。

稲の生育状態診断

若狭湾の赤潮発生調査
これまで宇宙開発は国家が行うものでしたが、現在、世界的に宇宙ビジネスの機運が高まっており、民間・自治体・大学による超小型衛星の開発やデータ利用が進んでいます。しかし、超小型衛星の実用化のためには高性能の地上局が必要であり、あわらキャンパスの地上局には大きな期待が寄せられています。今後、多くの超小型衛星のデータ受信が予定されていることに加え、福井工業大学でも超小型衛星を開発、10mパラボラアンテナによる高速通信機能を活かした様々な人工衛星ミッションに地域と協働してトライすることにより、私たちが宇宙をより身近に感じられる未来の実現に貢献していきます。